2018年02月23日
口内炎と間違えやすい口腔がん、AIで判別…阪大チームが開発へ
舌や歯茎などにできる 口腔こうくう がんを人工知能(AI)で判別するシステムの開発に、大阪大歯学部のチームが乗り出した。口腔がんは初期の病態が口内炎と似ており、気付くのが遅れるケースがあるという。チームは2年後の完成を目指しており、歯科医院に導入して早期治療につなげたい考え。家庭用・歯科用超音波スケーラー
口腔がんは舌や歯茎、頬粘膜などにでき、リンパ節や肺に転移することもある。だが、専門知識を持たない医師や歯科医師だとがんに気付かず、舌や顎の骨の切除が必要になるまで進行してしまうことが少なくなかった。チームの平岡慎一郎助教(口腔外科)らは、AIが大量の画像から自動的に特徴などを探し出す「ディープ・ラーニング(深層学習)」の技術を応用。口腔がんや類似する症状の画像5000~1万枚程度を学ばせ、自動的に口腔がんを見分けるシステムを作るという。エアーコンプレッサー
開発したシステムは歯科医院などでの診断支援に使う。将来的には患者個人が画像を撮影・送信することで早期判別につながる仕組み作りも検討している。
http://yaplog.jp/luccye/archive/255
口腔がんは舌や歯茎、頬粘膜などにでき、リンパ節や肺に転移することもある。だが、専門知識を持たない医師や歯科医師だとがんに気付かず、舌や顎の骨の切除が必要になるまで進行してしまうことが少なくなかった。チームの平岡慎一郎助教(口腔外科)らは、AIが大量の画像から自動的に特徴などを探し出す「ディープ・ラーニング(深層学習)」の技術を応用。口腔がんや類似する症状の画像5000~1万枚程度を学ばせ、自動的に口腔がんを見分けるシステムを作るという。エアーコンプレッサー
開発したシステムは歯科医院などでの診断支援に使う。将来的には患者個人が画像を撮影・送信することで早期判別につながる仕組み作りも検討している。
http://yaplog.jp/luccye/archive/255
Posted by oeney at
15:35
│Comments(0)
2018年02月23日
口腔機能の維持・向上へ 30年度診療報酬改定案を答申 ―中医協総会
中医協総会が2月7日、厚労省内で開催され、平成30年度診療報酬改定案を加藤勝信厚労大臣に答申した。超音波スケーラー
歯科関係では、ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、歯科疾患管理料について、口腔機能の発達不全が認められる小児のうち、特に機能不全が著しく継続的な管理が必要な患者に対する「小児口腔機能管理加算」100点を新設。また、老化等に伴い口腔機能の低下が認められる高齢者のうち、特に機能低下が著しく継続的な管理が必要な患者に対する評価の加算「口腔機能管理加算」100点を新設した。口腔内カメラ
周術期口腔機能管理の推進として、地域包括ケアシステムの構築に向けて医科歯科連携を推進する観点から、周術期口腔機能管理に係る一連の項目について、対象患者の拡大や明確化などの見直しを行った他、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、周術期口腔機能管理の実績を選択可能な要件の一つにした。
かかりつけ歯科医の機能評価では、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の見直しを行った。
在宅歯科医療の推進等では、効率的で質の高い在宅歯科医療の提供体制を確保するため、歯科訪問診療料や訪問歯科衛生指導料の評価の在り方を見直すとともに、入院患者や介護保険施設入所者等や通院困難な小児に対する口腔機能管理を充実させた。
歯科外来診療における院内感染防止対策を推進では、歯科初診料237点、歯科再診料48点にそれぞれ3点引き上げるとともに、歯科初・再診料に対して院内感染防止対策に関する施設基準(7項目)を新設した。また、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に院内感染防止対策に関する内容を追加した。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518418994
歯科関係では、ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、歯科疾患管理料について、口腔機能の発達不全が認められる小児のうち、特に機能不全が著しく継続的な管理が必要な患者に対する「小児口腔機能管理加算」100点を新設。また、老化等に伴い口腔機能の低下が認められる高齢者のうち、特に機能低下が著しく継続的な管理が必要な患者に対する評価の加算「口腔機能管理加算」100点を新設した。口腔内カメラ
周術期口腔機能管理の推進として、地域包括ケアシステムの構築に向けて医科歯科連携を推進する観点から、周術期口腔機能管理に係る一連の項目について、対象患者の拡大や明確化などの見直しを行った他、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、周術期口腔機能管理の実績を選択可能な要件の一つにした。
かかりつけ歯科医の機能評価では、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の見直しを行った。
在宅歯科医療の推進等では、効率的で質の高い在宅歯科医療の提供体制を確保するため、歯科訪問診療料や訪問歯科衛生指導料の評価の在り方を見直すとともに、入院患者や介護保険施設入所者等や通院困難な小児に対する口腔機能管理を充実させた。
歯科外来診療における院内感染防止対策を推進では、歯科初診料237点、歯科再診料48点にそれぞれ3点引き上げるとともに、歯科初・再診料に対して院内感染防止対策に関する施設基準(7項目)を新設した。また、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に院内感染防止対策に関する内容を追加した。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518418994
Posted by oeney at
15:23
│Comments(0)
2018年02月12日
いくらお金をかけても、天然歯以上にはならない
治療を受けた歯は、もちろん一時的には生活に支障をきたさなくなるだろうが、治療前と全く同じ状態に戻るわけではない。吉岡氏に言わせればそれは“歯のリフォーム”にすぎず、いくらお金をかけて治療したとしても、天然歯以上の歯にはならないという。家庭用・歯科用超音波スケーラー
「1本あたり40万円程度かかるインプラントですが、10年後も歯槽から脱落せずに残っている確率は90%程度。一方、痛みや炎症などの問題もなく、しっかり機能しているという成功率は60%程度に下がります。仮に85歳までに20本ほど歯を失い、全歯をインプラントに差し替えたとすると、40万円×20本でおおよそ800万円。しかも、その機能は天然歯に及ばないのです」 エアーコンプレッサー
そもそも、虫歯や歯周病の原因は何なのか。
「口内のバクテリア(細菌)ですね。虫歯は歯が溶けていく病気で、歯周病は歯を支える骨が溶ける病気ですが、どちらも原因は同じです。歯のセルフケアの基本はバクテリアを減らすこと。歯磨きも、歯の間に詰まった食べ残しを取ること以上に、バクテリアを減らすことが目的なのです。また、口内環境が悪いと、震災などの災害時の死亡原因のひとつでもある、誤嚥性肺炎を起こしやすくなります」
虫歯や歯周病の予防はバクテリアを取ることよりも、“バクテリアが増えにくい体質になる”ことに重きを置いてほしい、と吉岡氏は続ける。「そのために必要なセルフケアは、食生活、唾液、歯のメンテナンスの3つです」
http://yaplog.jp/luccye/archive/253
「1本あたり40万円程度かかるインプラントですが、10年後も歯槽から脱落せずに残っている確率は90%程度。一方、痛みや炎症などの問題もなく、しっかり機能しているという成功率は60%程度に下がります。仮に85歳までに20本ほど歯を失い、全歯をインプラントに差し替えたとすると、40万円×20本でおおよそ800万円。しかも、その機能は天然歯に及ばないのです」 エアーコンプレッサー
そもそも、虫歯や歯周病の原因は何なのか。
「口内のバクテリア(細菌)ですね。虫歯は歯が溶けていく病気で、歯周病は歯を支える骨が溶ける病気ですが、どちらも原因は同じです。歯のセルフケアの基本はバクテリアを減らすこと。歯磨きも、歯の間に詰まった食べ残しを取ること以上に、バクテリアを減らすことが目的なのです。また、口内環境が悪いと、震災などの災害時の死亡原因のひとつでもある、誤嚥性肺炎を起こしやすくなります」
虫歯や歯周病の予防はバクテリアを取ることよりも、“バクテリアが増えにくい体質になる”ことに重きを置いてほしい、と吉岡氏は続ける。「そのために必要なセルフケアは、食生活、唾液、歯のメンテナンスの3つです」
http://yaplog.jp/luccye/archive/253
Posted by oeney at
12:55
│Comments(0)
2018年02月12日
なぜ毎日歯磨きしても虫歯になるのか
毎日、歯磨きしているにもかかわらず、虫歯や歯周病で歯を失う人は後を絶たない。なぜだろうか。超音波スケーラー
「歯の健康を考えたとき、歯磨きは最重要事項ではありません。日頃の食生活や生活習慣、歯医者などでのケアを定期的に行っているかどうかのほうが、ずっと大切です」 口腔内カメラ
こう語るのは、『歯科治療費800万円節約術』などの著書がある、歯科医の吉岡秀樹氏だ。吉岡氏によれば、歯は30代半ばあたりから老化が顕著になるという。
「その前から歯は徐々にもろくなっていきますが、症状として表れてくるのが30代半ば以降ということです。厚生労働省の調査では、30代後半から40代前半になると28~32本ある天然歯のうち、平均12本程度が何かしらの治療を受けているそうです。ただ歯を磨いているだけでは、虫歯は予防できないのです」
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518331738
「歯の健康を考えたとき、歯磨きは最重要事項ではありません。日頃の食生活や生活習慣、歯医者などでのケアを定期的に行っているかどうかのほうが、ずっと大切です」 口腔内カメラ
こう語るのは、『歯科治療費800万円節約術』などの著書がある、歯科医の吉岡秀樹氏だ。吉岡氏によれば、歯は30代半ばあたりから老化が顕著になるという。
「その前から歯は徐々にもろくなっていきますが、症状として表れてくるのが30代半ば以降ということです。厚生労働省の調査では、30代後半から40代前半になると28~32本ある天然歯のうち、平均12本程度が何かしらの治療を受けているそうです。ただ歯を磨いているだけでは、虫歯は予防できないのです」
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518331738
Posted by oeney at
12:48
│Comments(0)
2018年02月11日
歯に穴をあける。複雑な治療の始まり
当時、徹底した手術が行われたのかどうか、抜歯が行われたのかどうかについては、残されている証拠が限られているため、議論が分かれる。家庭用・歯科用超音波スケーラー
だが、このような早い時期から、補綴(義歯)が作られていた可能性があるケースが3つある。古代エジプト人は、初めて金歯を使った。穴をあけてゴールドのワイヤで歯の間を縫うようにして複雑なスタイルを作り上げていた。おそらく歯をしかるべき位置で固定するためか、美容のためだったと思われる。エアーコンプレッサー
紀元前2500年には、今日では悪夢のような処置だと考えられている最初の歯科治療が生み出された。歯に穴をあけることだ。
当時の遺体を調べると、人工と思われる歯の外側に左右対称の小さな穴が開いているのがわかる。膿を出して腫瘍の圧迫を緩和するために穴をあけることを学んでいたようだ。現代医学の恩恵もない時代に、こうした処置を体験するなどとても考えられない。
http://yaplog.jp/luccye/archive/251
だが、このような早い時期から、補綴(義歯)が作られていた可能性があるケースが3つある。古代エジプト人は、初めて金歯を使った。穴をあけてゴールドのワイヤで歯の間を縫うようにして複雑なスタイルを作り上げていた。おそらく歯をしかるべき位置で固定するためか、美容のためだったと思われる。エアーコンプレッサー
紀元前2500年には、今日では悪夢のような処置だと考えられている最初の歯科治療が生み出された。歯に穴をあけることだ。
当時の遺体を調べると、人工と思われる歯の外側に左右対称の小さな穴が開いているのがわかる。膿を出して腫瘍の圧迫を緩和するために穴をあけることを学んでいたようだ。現代医学の恩恵もない時代に、こうした処置を体験するなどとても考えられない。
http://yaplog.jp/luccye/archive/251
Posted by oeney at
11:42
│Comments(0)
2018年02月11日
歯科治療の誕生は古代エジプトから
記録によると、歯科治療は、厳しい時代、食事事情も苦しかった古代エジプト人たちの文化で始まったという。超音波スケーラー
古代エジプトの人たちの食事は、おもに穀物だったが、安全なパンを作るのに、今日のようにきちんと殺菌された質のいい原料やいい家庭用品もなかった。口腔内カメラ
そのため、さまざまな金属、鉱物、体に悪そうなものがパンの中に入り込み、虫歯など多くの歯の障害を引き起こした。
エジプト人は食べ物から砂を取り除くことはほとんど不可能だとわかっていて、これは、当時蔓延していた口内の重大な健康問題の原因となっていた。
世界初の歯医者の記録は紀元前2660年頃にさかのぼり、ジョセル王の主席歯医者で内科医だったHesyre という人物だったという。
この時代のおもな歯科治療は、虫歯になったり、欠けたり、割れた歯や歯肉や膿傷に痛みを和らげるための詰め物をすることだった。
詰める物は、ハチミツやハーブなど植物、金のこともあったが、金を詰め物に使った歯科処置が死後に行われたのかどうかははっきりしない。とはいえ、この時代に行われた治療が、どれも耐えがたい痛みを伴ったことは確かだろう。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518160756
古代エジプトの人たちの食事は、おもに穀物だったが、安全なパンを作るのに、今日のようにきちんと殺菌された質のいい原料やいい家庭用品もなかった。口腔内カメラ
そのため、さまざまな金属、鉱物、体に悪そうなものがパンの中に入り込み、虫歯など多くの歯の障害を引き起こした。
エジプト人は食べ物から砂を取り除くことはほとんど不可能だとわかっていて、これは、当時蔓延していた口内の重大な健康問題の原因となっていた。
世界初の歯医者の記録は紀元前2660年頃にさかのぼり、ジョセル王の主席歯医者で内科医だったHesyre という人物だったという。
この時代のおもな歯科治療は、虫歯になったり、欠けたり、割れた歯や歯肉や膿傷に痛みを和らげるための詰め物をすることだった。
詰める物は、ハチミツやハーブなど植物、金のこともあったが、金を詰め物に使った歯科処置が死後に行われたのかどうかははっきりしない。とはいえ、この時代に行われた治療が、どれも耐えがたい痛みを伴ったことは確かだろう。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518160756
Posted by oeney at
11:38
│Comments(0)
2018年02月09日
日本国内にたった 3頭しかいない、病院に常勤し、子どもに寄り添うファシリティドッグ
国内初のファシリティドッグとして2010年から活動を担ってきた初代犬・ベイリーも10歳を迎えましたが、ファシリティドッグの認知度はまだまだ低い状況です。シャイン・オン!キッズは戌年の今年、「ファシリティドッグ写真展2018 こども病院で働くしっぽの仲間」の開催を機に、全国の病院にファシリティドッグのさらなる普及を目指し活動していきます。家庭用・歯科用超音波スケーラー
※こちらの写真展はTOOTH FAIRY(日本財団主催/日本歯科医師会協力)の支援により行わせていただきます。エアーコンプレッサー
初日のオープニングイベントには、神奈川県立こども医療センターで2頭で活動中のベイリーとアニー、静岡県立こども病院で働くヨギもやってきます。また、毎日午前と午後には読み聞かせや音楽など楽しいイベントも開催。アンケートに記入して頂いた先着 200 名様には銀座コージーコーナーの小犬サブレのプレゼントもあります。ご家族揃ってご来場ください。
※ファシリティドッグの体調によってはお休みをいただくこともございます。予めご了承ください。
http://yaplog.jp/luccye/archive/249
※こちらの写真展はTOOTH FAIRY(日本財団主催/日本歯科医師会協力)の支援により行わせていただきます。エアーコンプレッサー
初日のオープニングイベントには、神奈川県立こども医療センターで2頭で活動中のベイリーとアニー、静岡県立こども病院で働くヨギもやってきます。また、毎日午前と午後には読み聞かせや音楽など楽しいイベントも開催。アンケートに記入して頂いた先着 200 名様には銀座コージーコーナーの小犬サブレのプレゼントもあります。ご家族揃ってご来場ください。
※ファシリティドッグの体調によってはお休みをいただくこともございます。予めご了承ください。
http://yaplog.jp/luccye/archive/249
Posted by oeney at
12:43
│Comments(0)
2018年02月09日
秦野伊勢原歯科医師会 創立70周年を祝う
一般社団法人秦野伊勢原歯科医師会(新倉良一会長/112人)は2月3日、創立70周年を記念した祝賀会を鶴巻温泉(秦野市)にある『元湯 陣屋』で開催した。当日は会員ら約80人が出席。永年在籍表彰や歴代会長への感謝状贈呈などが行われ、地域の歯科医療の更なる発展と寄与に向けて心をひとつに活動していくことを誓った。超音波スケーラー
秦野伊勢原歯科医師会は1947年11月に前身となる中郡歯科医師会として発足。両市の市制施行などによる名称変更を経て1971年に現在の秦野伊勢原歯科医師会に。2013年には一般社団法人となった。現在の会員は秦野市68人、伊勢原市が44人。口腔内カメラ
祝賀会の冒頭、新倉会長は「70年という長きにわたり、先輩方が築いてきた実績と貢献に感謝しています。歯科医師会は地域に根差した活動が大切。これからの高齢化社会に向け、協力して地域社会に貢献していきたい」とあいさつ。
来賓を代表して(一社)神奈川県歯科医師会の鈴木駿介会長は「70周年おめでとうございます。これまでの社会の発展の源は、地域で活動してきた先生方がいるからこそ。築き上げた信頼関係を地域の包括ケアに活かして頑張っていただければ」と祝辞を述べた。
式では、在籍60年以上の山田金伍氏(山田歯科医院/秦野市柳町)をはじめ、40年以上の永年在籍会員20人に表彰状、過去10年の歴代会長に感謝状を贈呈。新人会員の紹介、餅つきや会員による演奏などの余興も行われ、会員らはさらなる協力体制を進めるため親睦を深めた。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518078858
秦野伊勢原歯科医師会は1947年11月に前身となる中郡歯科医師会として発足。両市の市制施行などによる名称変更を経て1971年に現在の秦野伊勢原歯科医師会に。2013年には一般社団法人となった。現在の会員は秦野市68人、伊勢原市が44人。口腔内カメラ
祝賀会の冒頭、新倉会長は「70年という長きにわたり、先輩方が築いてきた実績と貢献に感謝しています。歯科医師会は地域に根差した活動が大切。これからの高齢化社会に向け、協力して地域社会に貢献していきたい」とあいさつ。
来賓を代表して(一社)神奈川県歯科医師会の鈴木駿介会長は「70周年おめでとうございます。これまでの社会の発展の源は、地域で活動してきた先生方がいるからこそ。築き上げた信頼関係を地域の包括ケアに活かして頑張っていただければ」と祝辞を述べた。
式では、在籍60年以上の山田金伍氏(山田歯科医院/秦野市柳町)をはじめ、40年以上の永年在籍会員20人に表彰状、過去10年の歴代会長に感謝状を贈呈。新人会員の紹介、餅つきや会員による演奏などの余興も行われ、会員らはさらなる協力体制を進めるため親睦を深めた。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1518078858
Posted by oeney at
12:39
│Comments(0)
2018年02月08日
上あごと上唇にあった亀裂はきれいになり、食事も言葉も支障がなくなった
朝7時に始まった初日の手術は11件。術後の回診を終えると、午後10時を過ぎていた。4日間で0〜50歳の39人の手術が無事終わった。家庭用・歯科用超音波スケーラー
「当初は手術中によく停電し、ヘッドランプが欠かせなかった」と佐賀大名誉教授の香月武さん(80)。25年前、ベトナムの高官が「魚でなく釣り道具がほしい」と言ったのを覚えている。状況は良くなってきたが、今も診療隊を頼りにする患者は多い。「自力で医療ができるように。釣り道具の作り方まで工夫してくれたら。戦後日本もたどってきた道だ」と語る。エアーコンプレッサー
ベトナムでは、1986年以降のドイモイ(改革開放政策)がもたらした経済成長が続く。全般に医療水準は改善してきたものの、都市と地方の格差は大きく、グエンディンチュー病院のような中核病院には患者が集中。医療スタッフや機器などの絶対数も不足し、本来の機能を果たすのが困難な状況だ。
「最新を提供し続けることが大事」と、協会常務理事の夏目長門・愛知学院大歯学部教授(60)。協会の活動は、病院の施設整備や貧困家庭への自立支援プログラム、現地人材の育成、学術調査・研究など徐々に広がりを見せている。
今回の派遣には、3年前から愛知学院大に留学しているグエンディンチュー病院の口腔外科医トラン・リー・ユイさん(33)も参加した。手術の技術習得のほか、協会がこれまで治療した3千人以上の血液サンプルを使った日越協力の遺伝子研究にも取り組む。
派遣中、ベンチェ省「日越医学友好学会」が設立された。省内の病院から350人が参加し、情報交換と医療の底上げを目指す。会場で初めての研究論文を発表したトランさんが、少し誇らしげに語った。「日本で学んだことが故郷の医学の発展に生きる。日越のかけ橋になれてうれしい」
http://yaplog.jp/luccye/archive/247
「当初は手術中によく停電し、ヘッドランプが欠かせなかった」と佐賀大名誉教授の香月武さん(80)。25年前、ベトナムの高官が「魚でなく釣り道具がほしい」と言ったのを覚えている。状況は良くなってきたが、今も診療隊を頼りにする患者は多い。「自力で医療ができるように。釣り道具の作り方まで工夫してくれたら。戦後日本もたどってきた道だ」と語る。エアーコンプレッサー
ベトナムでは、1986年以降のドイモイ(改革開放政策)がもたらした経済成長が続く。全般に医療水準は改善してきたものの、都市と地方の格差は大きく、グエンディンチュー病院のような中核病院には患者が集中。医療スタッフや機器などの絶対数も不足し、本来の機能を果たすのが困難な状況だ。
「最新を提供し続けることが大事」と、協会常務理事の夏目長門・愛知学院大歯学部教授(60)。協会の活動は、病院の施設整備や貧困家庭への自立支援プログラム、現地人材の育成、学術調査・研究など徐々に広がりを見せている。
今回の派遣には、3年前から愛知学院大に留学しているグエンディンチュー病院の口腔外科医トラン・リー・ユイさん(33)も参加した。手術の技術習得のほか、協会がこれまで治療した3千人以上の血液サンプルを使った日越協力の遺伝子研究にも取り組む。
派遣中、ベンチェ省「日越医学友好学会」が設立された。省内の病院から350人が参加し、情報交換と医療の底上げを目指す。会場で初めての研究論文を発表したトランさんが、少し誇らしげに語った。「日本で学んだことが故郷の医学の発展に生きる。日越のかけ橋になれてうれしい」
http://yaplog.jp/luccye/archive/247
Posted by oeney at
12:27
│Comments(0)
2018年02月08日
口唇口蓋裂診療隊 25年目のベトナム派遣
NPO法人「日本口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)協会」(事務局・名古屋市千種区)の診療隊がベトナム・ベンチェ省で無償手術を始めて25年。全国の口腔(こうくう)外科医や看護師ら48人が参加した昨年12月の派遣では、現地に根付いた支援の新たな芽吹きも見て取れた。超音波スケーラー
「お母さんに抱っこしてもらうのが一番。これで一気におとなしくなる」。診療隊が活動するグエンディンチュー病院。手術後の患者が運び込まれる回復室で、中部大教授の小児科医、馬場礼三さん(61)が笑った。麻酔からさめて泣いていた生後8カ月の男の子ファン・フー・クイちゃんが、母フンさん(34)の胸で安らかな顔を見せた。口腔内カメラ
「こんなに小さくて手術は初めてだから昨夜は心配で。この子は寝ていたけど私は寝られなかった」。疲れた顔のフンさんが、やっとうれしそうに打ち明けた。次男クイちゃんは昨春にこの病院で産んだ。妊娠中に口唇裂が分かり悩んだが、診療隊のことを教わり、ずっと待っていたという。
「どこのお母さんも一緒なんだなと思います」と派遣10年目の愛知学院大歯学部の口腔外科医、井村英人さん(39)。手術前はご飯ものどを通らない。気丈にしていても、無事に終わって安堵(あんど)と喜びで泣きだす人もいる。「治療の原点に立ち返る。保護者の不安を少しでも取り除くサポートが日本でもできれば」と話す。
「アリガト」。おさげ髪のグエン・ティ・フィン・ユイちゃん(6つ)は、ベッドの上で覚えたばかりの日本語を繰り返し、手を振った。診察日の23日午前3時、姉に抱えられ、150キロ離れた自宅から母親のバイクで駆けつけた。一家は日雇いで生活が苦しく治療をあきらめかけたが、母が親戚に診療隊のことを聞き、治療につながった。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1517988493
「お母さんに抱っこしてもらうのが一番。これで一気におとなしくなる」。診療隊が活動するグエンディンチュー病院。手術後の患者が運び込まれる回復室で、中部大教授の小児科医、馬場礼三さん(61)が笑った。麻酔からさめて泣いていた生後8カ月の男の子ファン・フー・クイちゃんが、母フンさん(34)の胸で安らかな顔を見せた。口腔内カメラ
「こんなに小さくて手術は初めてだから昨夜は心配で。この子は寝ていたけど私は寝られなかった」。疲れた顔のフンさんが、やっとうれしそうに打ち明けた。次男クイちゃんは昨春にこの病院で産んだ。妊娠中に口唇裂が分かり悩んだが、診療隊のことを教わり、ずっと待っていたという。
「どこのお母さんも一緒なんだなと思います」と派遣10年目の愛知学院大歯学部の口腔外科医、井村英人さん(39)。手術前はご飯ものどを通らない。気丈にしていても、無事に終わって安堵(あんど)と喜びで泣きだす人もいる。「治療の原点に立ち返る。保護者の不安を少しでも取り除くサポートが日本でもできれば」と話す。
「アリガト」。おさげ髪のグエン・ティ・フィン・ユイちゃん(6つ)は、ベッドの上で覚えたばかりの日本語を繰り返し、手を振った。診察日の23日午前3時、姉に抱えられ、150キロ離れた自宅から母親のバイクで駆けつけた。一家は日雇いで生活が苦しく治療をあきらめかけたが、母が親戚に診療隊のことを聞き、治療につながった。
http://ulog.u.nosv.org/item/adental/1517988493
Posted by oeney at
12:24
│Comments(0)
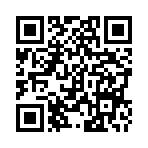
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン







