2018年09月18日
第48回日本口腔インプラント学会学術大会 開催される
9月14日(金)~16日(日),大阪国際会議場(大阪市北区)において標記学会が「インプラント治療が拓く未来 超高齢社会への責任」をテーマに開催された〔大会長:馬場俊輔氏(大歯大),名誉大会長:川添堯彬氏(大歯大)〕.家庭用・歯科用超音波スケーラー
シンポジウム8「ソフトティッシュインテグレーション~軟組織付着に関する臨床と研究の現状と将来~」では,船登彰芳氏(近畿・北陸支部)が「臨床におけるインプラント周囲のソフトティッシュマネージメント」として臨床家の立場から,インプラント治療における清掃性確保のために角化歯肉の獲得が望ましいこと,審美性の確保のために歯肉の垂直的・水平的厚みを確保し骨吸収を防ぐ手立てが求められることを文献的に考察.歯肉退縮を防ぐうえでSupracrestal tissue attachment(生物学的幅径)を維持するための軟組織の封鎖性とその予知性の獲得の重要性を指摘し問題提起とした.これを受けて研究者の立場から軟組織の封鎖性を獲得するために取り組んだ研究の報告がなされ,まず鮎川保則氏(九大)が「インプラント周囲組織における生物学的幅径と軟組織封鎖性」としてインプラント体の表面性状について研磨面,粗造面のメリット・デメリットを整理したうえで,表面の塩化カルシウム水熱処理により天然歯と同等の上皮付着や細胞接着を獲得できたとした.エアーコンプレッサー
さらに山田将博氏(東北大)が「バイオミメティックインプラントによる軟組織付着獲得への挑戦」,ナノテクノロジー応用によるインプラント体のへセメント質模倣チタン表面付与による結合組織付着の評価から,ナノ表面に密な線維再構築とインプラント体への垂直的線維配向が見られたとした.
シンポジウム10「海外の基礎研究はインプラント治療をどう変えたか?―From Basic to Clinic―」では,加来 賢氏(新潟大)が「骨質をコラーゲンの生合成から理解する―個別化インプラント治療を可能とするための基礎研究―」として骨のコラーゲン架橋を個別化診断のマーカーに応用する/人為的に制御する可能性について,神野洋平氏(マルメ大)が「インプラント周囲組織の反応 種々の検証から見えてくるもの」としてアンダーサイズドリリングでの埋入が周囲骨に与える影響について,鬼原英道氏(岩医大)が「インプラント周囲炎予防のための基礎的研究―ハーバード大学との共同研究―」としてインプラント周囲の上皮付着の温存ならびに剥離後の再付着の可能性について,研究知見を示した.
https://yaplog.jp/luccye/archive/490
シンポジウム8「ソフトティッシュインテグレーション~軟組織付着に関する臨床と研究の現状と将来~」では,船登彰芳氏(近畿・北陸支部)が「臨床におけるインプラント周囲のソフトティッシュマネージメント」として臨床家の立場から,インプラント治療における清掃性確保のために角化歯肉の獲得が望ましいこと,審美性の確保のために歯肉の垂直的・水平的厚みを確保し骨吸収を防ぐ手立てが求められることを文献的に考察.歯肉退縮を防ぐうえでSupracrestal tissue attachment(生物学的幅径)を維持するための軟組織の封鎖性とその予知性の獲得の重要性を指摘し問題提起とした.これを受けて研究者の立場から軟組織の封鎖性を獲得するために取り組んだ研究の報告がなされ,まず鮎川保則氏(九大)が「インプラント周囲組織における生物学的幅径と軟組織封鎖性」としてインプラント体の表面性状について研磨面,粗造面のメリット・デメリットを整理したうえで,表面の塩化カルシウム水熱処理により天然歯と同等の上皮付着や細胞接着を獲得できたとした.エアーコンプレッサー
さらに山田将博氏(東北大)が「バイオミメティックインプラントによる軟組織付着獲得への挑戦」,ナノテクノロジー応用によるインプラント体のへセメント質模倣チタン表面付与による結合組織付着の評価から,ナノ表面に密な線維再構築とインプラント体への垂直的線維配向が見られたとした.
シンポジウム10「海外の基礎研究はインプラント治療をどう変えたか?―From Basic to Clinic―」では,加来 賢氏(新潟大)が「骨質をコラーゲンの生合成から理解する―個別化インプラント治療を可能とするための基礎研究―」として骨のコラーゲン架橋を個別化診断のマーカーに応用する/人為的に制御する可能性について,神野洋平氏(マルメ大)が「インプラント周囲組織の反応 種々の検証から見えてくるもの」としてアンダーサイズドリリングでの埋入が周囲骨に与える影響について,鬼原英道氏(岩医大)が「インプラント周囲炎予防のための基礎的研究―ハーバード大学との共同研究―」としてインプラント周囲の上皮付着の温存ならびに剥離後の再付着の可能性について,研究知見を示した.
https://yaplog.jp/luccye/archive/490
Posted by oeney at 17:25│Comments(0)
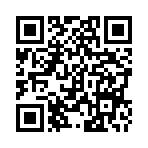
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






